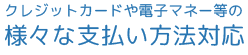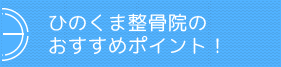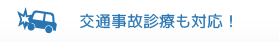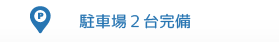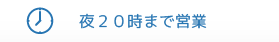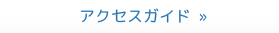みんなは「腱鞘炎(けんしょうえん)」や「ばね指」って聞いたことあるかな?指を動かすと痛かったり、引っかかったりする、あの症状のことだね。
実はこれらの症状、ただの「使いすぎ」だけじゃないんだ。体の首や肩の近くにある神経がギュッと圧迫されてることが原因になっていることがあるんだよ!
今日は、普段あんまり聞かないけど、とっても大切なこの関係について、わかりやすく説明していくね!
1.なんで「神経の元気がない」と体が困るの?
僕たちの体は、脳から「こう動いてね!」っていう電気信号を受け取って動いているんだ。この電気信号が通る道(神経)が、どこかでぎゅっと押されちゃうと、信号がうまく届かなくなって、筋肉の動きが悪くなったり、痛みやしびれが出たりするんだ。
特に、首から肩、腕の方に大切な神経の束が通っていて、その神経が胸の出口のあたり(鎖骨と肋骨の間や、小さい筋肉の下)で圧迫されると、「胸郭出口症候群(きょうかくでぐちしょうこうぐん)」っていう状態になるんだよ。
じゃあ、この神経の圧迫が、どうして手や指の症状に関係するんだろう?
2.「ばね指」と「胸郭出口症候群」は家族みたいな関係?!
指を曲げ伸ばしするときに、カクンと引っかかる「弾発指(だんぱつゆび)」、つまり「ばね指」は、指の使いすぎだけでなるわけじゃないんだ。神経が元気がないことが原因でなることも少なくないんだよ。
実は、胸の出口で神経が圧迫されたり、手首の中にある「手根管(しゅこんかん)」っていうトンネルで神経がギュッとされたり(これを手根管症候群っていうよ)すると、神経の働きが弱まっちゃうんだ。これがばね指の大きな原因になることがあるんだよ。
だから、もしばね指がなかなか治らないって場合は、単に指を使いすぎただけじゃなくて、胸郭出口症候群や手根管症候群がもとになっていることがあるって知っておくといいかも。
親指以外の指がばね指になるのも同じなんだ。神経が元気がないと、本当はなんでもないくらいの軽い作業でも、指にとっては「がんばりすぎ」になっちゃって、最初はちょっとした腱鞘炎になって、それがひどくなって本格的なばね指になっちゃうんだよ。
3.「腱鞘炎」だって神経と関係あるよ!
腱鞘炎は、指を使いすぎると、腱(けん)の周りにある液体(滑液)がたくさん出すぎて炎症を起こすことだよね。でも、さっき話した神経の元気がない状態は、この腱鞘炎が始まるきっかけになることも多いんだ。
神経の働きが弱くなると、腕の筋肉の力も落ちちゃうんだ。そうすると、指の関節にかかる負担がどんどん大きくなって、腱鞘炎になるリスクが高くなっちゃうんだよ。
さらに、胸郭出口症候群で腕の神経が邪魔されると、手根管症候群になることも多いんだ。手根管症候群は手首のトンネルが狭くなる病気だけど、その根本的な原因は、やっぱり神経の元気がないことで筋肉が弱っちゃうことにあるんだ。筋肉が弱ると、腱やじん帯をしっかり守れなくなって、手首のトンネルが狭くなり、最終的に指の症状が出てくるんだよ。
4.どうすればよくなる?解決へのヒント!
これらの症状は、実はみんなつながっているから、よくするためにはいくつか大事なポイントがあるんだ。
- まずは、神経の通り道をスッキリさせよう! 腱鞘炎やばね指が神経の元気がないせいだとしたら、指だけをどうにかしても、なかなか根本からは解決しないよね。だから、まずは胸の出口で神経が圧迫されているのを解決することがすごく大切なんだ。もし神経の圧迫をそのままにして、無理に腕の筋肉を動かそうとすると、かえって症状が悪化する「神経筋閉塞(しんけいきんへいそく)」っていう、強いリバウンドが起きる危険もあるから注意が必要だよ。
- 腕の筋肉も大事だよ! ばね指や腱鞘炎をよくするには、腕の筋肉をしっかりケアすることもとっても大切なんだ。腕の筋肉は、指の関節にかかる衝撃を吸収してくれる「クッション」みたいな役割があるんだよ。このクッションの働きを元に戻すことで、指への負担を減らして、症状がよくなりやすくなるんだ。
- 焦らず、じっくり治していこう! 胸郭出口症候群や手根管症候群は、時間がたつとだんだん進んでいくものなんだ。だから、すぐにはパッと治るわけじゃなくて、少しずつ、段階を踏んでよくしていく必要があるんだよ。焦らず、じっくり向き合っていこうね。
まとめ
腱鞘炎やばね指って、ただの「使いすぎ」って思われがちだけど、実はその奥には、胸郭出口症候群による神経の圧迫や、それによって神経が元気なくなっちゃうこと、筋肉が弱くなっちゃうことなんかが深く関係していることがあるんだ。
もし、手や指の痛みがなかなか治らない場合は、これらの根本的な原因を探ることが、症状をよくするための近道になるかもしれないよ。
もし気になる症状があったら、一人で悩まずに、学校の先生や家族、またはお医者さんや詳しい人に相談してみようね!