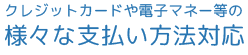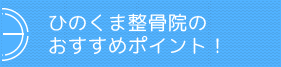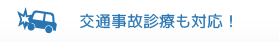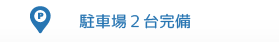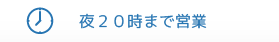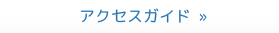歩くと膝が痛い、曲がらない。
しかも膝に水がたまっている——。
そんなお悩みの方に向けて、
関節水腫や半月板損傷の原因、
整形外科での対応との違い、
そして当院で行っている
「神経筋整復法」による治療について
分かりやすく解説いたします。
膝に水がたまるとは?関節水腫の基礎知識
膝の中にたまる「水」の正体
「膝に水がたまる」と聞くと、
膝の中に水道水のような液体が
たまっているようなイメージを
持たれるかもしれません。
しかし実際には、関節内で分泌される滑液(かつえき)と呼ばれる関節の潤滑油のような成分が、異常に増えてしまった状態のことを指します。
この状態は医学的には
「関節水腫(かんせつすいしゅ)」と呼ばれ、
膝関節を構成する軟骨や靭帯、
半月板などにダメージが起きたときに
防御反応として発生することが多いです。
水がたまるメカニズムと原因疾患
膝の関節は「関節包(かんせつほう)」という袋に
覆われていて、その内部で関節液が産生されます。
普段は関節がスムーズに動くように、
最小限の滑液だけが分泌されていますが、
関節内で炎症が起こると滑液が異常に分泌され、水がたまったように腫れてきます。
このような水がたまる原因としては
以下のような疾患や外傷が挙げられます:
- 変形性膝関節症
- 関節リウマチ
- 半月板損傷
- 靭帯損傷(前十字・内側側副など)
- 膝蓋下脂肪体炎
このうち特に多いのが変形性膝関節症と
半月板損傷です。これらは中高年層に多く、
膝の痛み・腫れ・違和感を訴える原因として
よく見られます。
半月板損傷とは?膝のクッション機能が崩れるとき
半月板は「膝のショックアブソーバー」
半月板とは、膝関節の中にある
C型をした軟骨組織で、
太ももの骨(大腿骨)とすねの骨(脛骨)の間に
挟まるように存在しています。
役割は主に以下の通りです:
- 衝撃吸収(クッションの役割)
- 関節の安定性の保持
- 関節面の圧力分散
- 関節軟骨の保護
この半月板が正常に働くことで、
歩行や階段の上り下り、しゃがみ動作など
日常生活の動作がスムーズに行えるのです。
半月板が損傷すると何が起きる?
一度傷ついた半月板は
自己修復が難しい組織です。
特に中央部は血流が乏しく、
自然治癒しにくい構造になっています。
損傷すると以下のような症状が現れます:
- 膝の曲げ伸ばし時の痛み
- 関節内の引っかかり感(ロッキング)
- 階段昇降時の不安定さ
- 膝に水がたまる(関節水腫)
また、半月板が損傷したまま放置すると、
関節の摩耗が進行し、変形性膝関節症へ
進行するリスクが高まります。
つまり、半月板損傷は「単なる膝の痛み」では終わらず、将来的な膝機能低下につながる重大なサインです。
膝の水・痛み・損傷…どう診断される?
診断には画像検査が基本
膝の水がたまる、痛い、動かしにくい——
このような症状が出たとき、
一般的な整形外科ではまず
画像検査を中心とした診断が行われます。
主に使われる検査は以下の通りです:
- X線(レントゲン)検査
→骨の変形や関節の隙間の狭さを評価 - MRI検査
→半月板や靭帯、関節水腫の状態を詳細に観察 - 関節穿刺(かんせつせんし)
→水(滑液)を抜いて成分を調べる
画像ではわからない「動きの情報」
ただし、これらの検査は
あくまで静止状態での構造異常の確認に過ぎません。
例えばMRIで半月板損傷が確認されたとしても、
「どの動きで痛むか」「なぜ痛みが続くのか」
「どうすれば改善するか」といった
機能的な評価までは見えてきません。
当院では、画像診断に頼りきらず、
実際の動きや筋肉の働きのバランスを
徹底的に確認することで、
痛みの根本原因を見極めていきます。
なぜ水がたまる?根本原因は“動作ストレス”
水がたまる=炎症反応のサイン
関節に水がたまる現象は、
医療的には「関節水腫」と呼ばれます。
これは体が関節内で起きている
炎症や損傷を修復しようとする反応の一種です。
主なきっかけは以下のようなものです:
- 半月板の損傷
- 靭帯の損傷や緩み
- 軟骨のすり減り
- 無理な動作による摩耗や衝突
- 慢性的な筋肉の偏り(アンバランス)
関節内に異常が起きると、
関節液(滑液)が過剰に分泌され、
関節内に水がたまることで腫れや圧痛を感じます。
動作の“くせ”が炎症を招く
特に重要なのは、
なぜその炎症が起きたのか?
という「背景」に着目することです。
実際には、こうしたケースがよくあります:
- 片脚に重心をかける立ち姿勢
- 太もも前側の筋肉(大腿四頭筋)の過緊張
- しゃがみ動作の繰り返しによる負担
- 足首・股関節の動きの制限による膝への代償動作
つまり、水がたまる症状の根本には
繰り返される日常の動作ストレスがあり、
その結果として膝関節内に炎症が起こっているのです。
そのため、単に水を抜くだけではなく、炎症を起こさない身体の使い方を取り戻すことが本質的な治療のカギとなります。
なぜ治らない?半月板損傷にありがちな誤解
誤解①:「安静にしていれば治る」
半月板損傷をはじめ、
膝に水がたまる症状が出ると
「とにかく安静に」と言われがちです。
たしかに急性期は安静が有効ですが、いつまでも動かさないことは逆効果です。
関節周囲の筋肉が硬くなり、
血流も低下するため、
回復力がかえって落ちてしまいます。
また、安静によって
正しい動き方を忘れてしまい、
再発のリスクが高くなるケースもあります。
誤解②:「筋トレすれば改善する」
膝の痛みに対してよく指導されるのが
太もも(大腿四頭筋)の筋トレです。
しかし、これは症状を悪化させる可能性があります。
理由はシンプルです:
- 筋肉に疲労が蓄積し、かえって緊張が強まる
- 痛みのある部位に無理な負荷がかかる
- 動作パターンの修正がされないまま鍛えても逆効果
当院では、
「痛んでいる筋肉を鍛えさせない」ことを
明確に治療方針として掲げています。
誤解③:「水を抜けば治る」
関節に水がたまると、
医療機関で「関節穿刺」を行い
注射器で水を抜く処置が行われます。
一時的に膝が楽になったように感じますが、根本原因が解決していなければ再発します。
水がたまる→抜く→またたまる
という負のループに入ってしまい、
かえって関節内環境を悪化させる可能性もあります。
だからこそ必要なのが、動きそのものを整える施術なのです。
神経筋整復法で行う“動きの修復”
ゴルジ腱器官へのアプローチで筋肉がゆるむ
神経筋整復法では、
痛みのある関節を「動かさずに安静にする」のではなく、
あえて安全な範囲で関節を動かしながら施術します。
その目的は、
筋肉の腱にあるゴルジ腱器官に刺激を与え、
筋肉を反射的に緩めること。
これは、力を加え続けると
筋肉が「これ以上は危険」と判断して
自動的に力を抜く生理現象を活用しているのです。
動的PNFから進化した“静的PNF”
本来、PNF(固有受容性神経筋促通法)は
最大可動域まで動かした関節から、
「力を入れて元の位置に戻そうとする」
動的なパターンが特徴です。
神経筋整復法では、
それをさらに静的に発展させ、
可動域の限界で静止→さらに少しだけ広げる刺激
という手法を取ります。
このとき、
腱と筋腹の間にあるゴルジ腱器官が反応し、
筋肉の過緊張を和らげる効果をもたらします。
他の施術法との違い
- マッサージ・指圧
→筋肉の表層しか刺激できないため、
深部の緊張が残ることが多い - 整体・カイロ・アジャスト
→関節を一気に動かすことで神経反射を狙うが、
筋肉の緊張状態や癖に対応しづらい - 電気療法・温熱療法
→一時的な鎮痛効果はあるが、
筋肉のバランスや動作の再教育はできない
神経筋整復法は、
“動きの中で神経と筋肉の協調を整える”
ことを主眼に置いた、極めて実践的な手技療法です。
「筋トレをさせない」理由と施術方針
痛んでいる筋肉に“負荷”をかけない
ひのくま整骨院では、
膝の痛みに対して筋トレを一切勧めていません。
その理由は明確です。
- 炎症が起きている筋肉に負荷をかければ、
さらに緊張と疲労が重なり悪化するから - 正しい動きができないまま筋トレを行えば、
動作の癖が強化され、再発リスクが高まるから
筋肉を鍛える前に必要なのは、
動きを整えて緊張を解くことです。
「動きながら治す」ための施術設計
当院では、患部をテーピングやサポーターで
固定して休ませるような処置を極力避けます。
なぜなら固定により、
- 関節の可動域が狭まり
- 筋肉が使われずに弱くなり
- バランスがさらに崩れる
という悪循環が生まれるからです。
神経筋整復法によって
「動きの中で」痛みなく筋肉を緩め、
本来の可動域と動作パターンを取り戻すことで、
回復を加速させます。
電気や温熱治療に頼らない理由
当院では電気治療や温熱機器も使いません。
- 一時的に痛みが和らぐだけで、
動きそのものが変わらない - 機械任せでは、筋肉の使い方・癖を見抜けない
そのため、当院では
施術者の手で直接、動きのズレを見極め、
筋肉の反応を細かく調整することにこだわっています。
これが、ひのくま整骨院が
「筋トレをさせず」「固定もせず」「電気も使わない」
というスタンスを徹底している理由です。
当院の対応と、来院前に知っておきたいこと
問診と検査で「痛みの根本」を見極める
ひのくま整骨院では、
まず徹底的な問診と触診を行います。
いつから痛いのか
どんな動きで悪化するのか
過去に膝を痛めた経験はあるか
それらを丁寧にヒアリングし、
関節の動きや筋肉の緊張状態を確認して、
“原因筋”の特定に努めます。
手技のみで施術。施術時間の目安は?
当院では電気や器具を使わず、
すべて手技による神経筋整復法で施術します。
1回の施術時間はおおよそ20〜30分程度。
初回は問診・検査に時間を要するため
60分前後を目安としてください。
回復までの通院目安とアドバイス
膝関節の痛みや関節水腫、半月板損傷の回復には、
状態により異なりますが、
3〜5回程度の施術で変化が出るケースが多くあります。
また、再発防止のために
歩行や立ち上がり方の指導も実施しています。
無理にトレーニングさせるのではなく、
「自然に正しい動きができる身体」に戻すためのサポートです。
このような方は、ぜひ当院へ
- 湿布と痛み止めしか出されなかった
- 筋トレを勧められて悪化した
- 整形外科で異常なしと言われたが痛い
- 水が溜まっては抜く…を繰り返している
- 手術は避けたいと思っている
あなたのその痛み、筋肉の誤作動が原因かもしれません。
来院のご案内|ひのくま整骨院
所在地:〒346-0012 埼玉県久喜市栗原2‐2‐7
診療時間:月~金 午前8:30~午後1:00/午後3:00~午後8:00、土曜のみ午前8:30~午後1:00/午後3:00~午後5:00
休診日:日曜・祝日
アクセス:JR・東武久喜駅東口からバス乗車、青毛三丁目停留所下車徒歩1分/東武幸手駅西口から徒歩13分/駐車場完備2台
電話予約:0480‐31‐7775